「山内タバコ禁止」高幡山明王院金剛寺(高幡不動尊)
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...
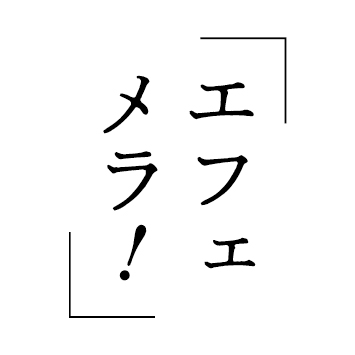
エフェメラ!
エフェメラ!
2025年8月5日
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶともなしに記録しようと思う。言葉は儚いものであるからこそ、今このときを確実に残してくれるから。
「今回、「幻の一九七九年論」たるこの評論集を構成するに当たって、あえて、その若書きの評論を、評論集の折り返し部分に置いてみた。単に現在から一九七九年を振り返るのではなく、一九七九年から未来への視点も交差させることで、一つの遠近感が得られるのではないかと思って。」
坪内祐三
2日連続で恐縮なのだけれど、今回も神保町・東京古書会館で開催された古本フェスタで手に入れた本から。坪内祐三『後ろ向きで前へ進む』の「あとがき」の一節を引用しました。
『後ろ向きで前へ進む』は、僕が持っていない、数少ない坪内祐三本のひとつ(おそらく著書の85%は持っている)で、とても気になる1冊だった(古本屋で見かけない本だけど500円で手に入れることができた)。気になっていたのは、そのタイトル。マーシャル・マクルーハンの共著『メディアはマッサージである』に登場する印象的な一節に由来しているのだろうと思って。その一節は「われわれはバックミラーごしに現在を見ている。われわれは未来にむかって後ろ向きに行進している」。でも、おそらくこれは勘違い。少なくとも今のところ、本書でマクルーハンは触れられていないから。
閑話休題。古本・新刊を問わず本を手にしたときには、まず目次を眺めて、そのあとにあとがきを読むことにしている。これはそれこそ坪内祐三がどこかで書いていたことで、真似をし始めたらすっかり癖になってしまった。
というわけでまず目次を眺めると、その最終章のタイトルに「東京堂書店のこと」とあるのが目に飛び込んでくる。東京古書会館からも近く、坪内祐三も常連だった居酒屋「浅野屋」と同じ通りの並びにある、新刊書店のこと。当然、坪内祐三が「東京堂書店」に足繁く通っていたことは知っている(かつて店内に、坪内祐三が古本市で購入した古本が並ぶ「坪内祐三棚」もあった)から、その章をまず読んでみたくなる。なんせ、今まさにすぐ近くにいるのだ。でも、癖なので、一度「あとがき」に飛んでいく。すると上のように書いてあった。
もちろん、どのページから読むかは読者の自由。ただ、この「あとがき」を読んで、章の並び順に込められた明確な意図を知ってしまった僕は、やはり思い直して、1つ目の章から順に読み進めていくことにした。これがあとがきを先に読む効能のひとつ。今ちょうど「折り返し」たところだ。(005)
エフェメラ/「一日だけの、短命な」を意味するギリシャ語「ephemera」。転じて、チラシやポスターなど一時的な情報伝達のために作成される紙ものなどを指す。短命だからこそ、時代を映すとされ、収集の対象になっている。

アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...
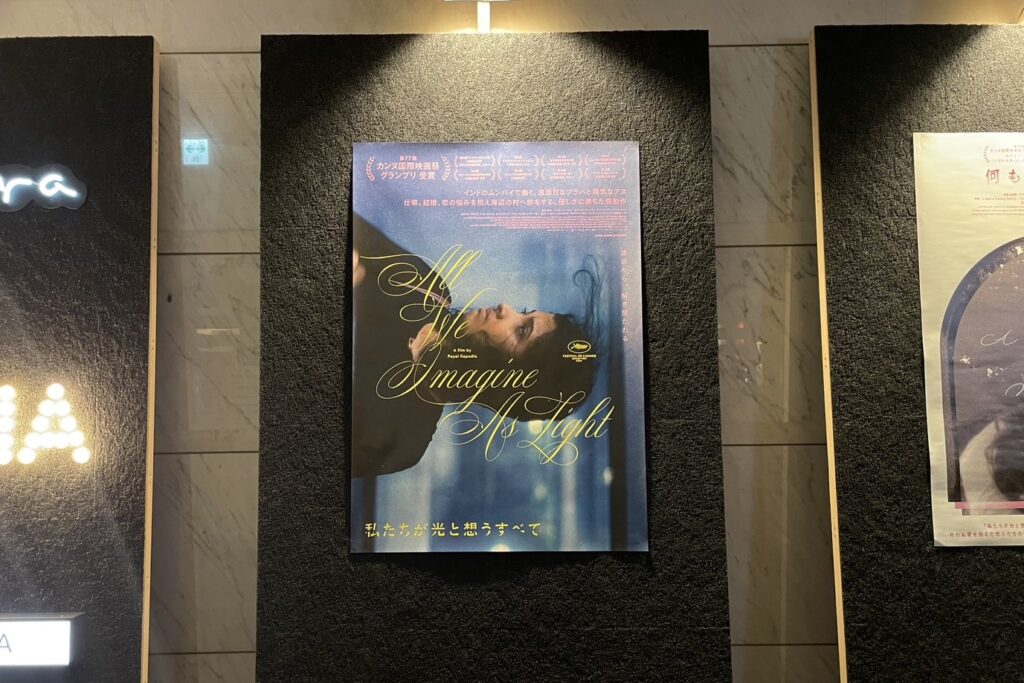
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...
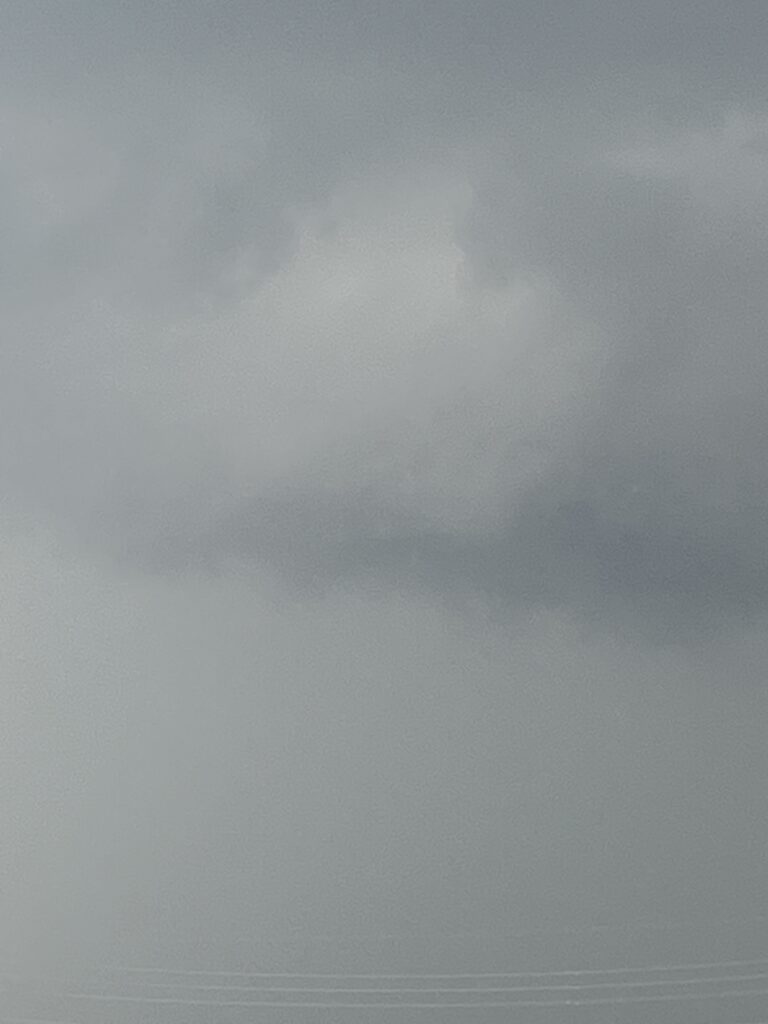
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...