アシナガバチの巣が大きい
8月最後の日曜日、長袖来て首にタオルも巻き、万全の蚊対策をして庭の草むしり。 庭の梅の木の茂みに今年はアシナガバチが巣を...
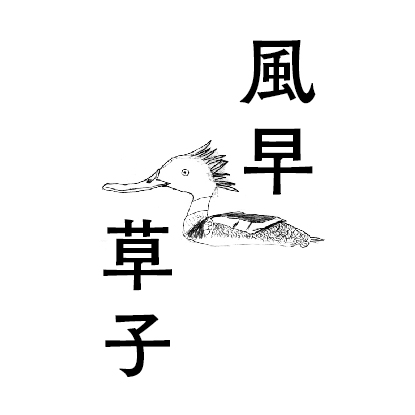
風早草子
カザハヤソウシ
2025年1月21日

長女は今日からまたインターンへ。朝、駅まで送る。今回は2週間、茨城県だそう。
就活期の長女、企業に関するニュースにも興味があるようだが、しばしば、色々聞かれる。最近だと「USスチールの話ってさー、あれってどうなの?」とか。
「あれってどうなの?」にざっくり答えるのは、ちょっと簡単じゃないぞ。
そもそも鉄って、ということもあるし、アメリカっていう国は、という話もあるし、労働組合っていうのは・・・みたいなこともある。そしてトーさんはアメリカ社会や経済の専門家ではない。まあでも、長く報道の世界にいるから、子どもよりは色々知ってることはある。製鉄所は結構何箇所か行ってるな。NKKとか、川鉄とか、みんな名前が変わってる。JFEになってからも行ってるけど。ミッタルとかアルセロールとか、この20年くらいの再編の歴史もあるし。知ってることは教えてやるが、要は「トーさんはどう思う?」と聞かれているので、それなりに自分の思うところを話す。
世の中は本質的に複雑だ。どう捉えるかは、人によって様々で一つの正解とか真実というのは無い。なので、色々な人の考えを聞いたり、媒体の情報を様々見た上で、自分なりの解釈、判断を下すという作業が常に必要だ。嘘や出鱈目がこれほどネットで流れる今の時代、そういうリテラシーは、とても重要なので、子どもたちには小さい時からそれは叩き込んできた。
ルールや規則が明確に定まっていない中、ネットで確信犯的にフェイク情報を発信するものが多々いて、それをまた信じ込んで拡散するものが多数いる現在の社会、子どもたちには、それぞれ自分の判断ができるリテラシーを身につけて欲しいと思っている。経験的にいえば、ネットであれ、メディアの報道であれ、専門家の解説であれ、分かりやす過ぎる話、あまりにシンプルな言説は、嘘を含んでいる。世の中は本質的に複雑だから。でも多くの人はその複雑さに付いてこれない。それでメディアにしても、様々な枝葉末節のディテールを省略、割愛して分かりやすいストーリーを作って伝える。それはある意味、仕方ない。だが、その度合いに応じて、「嘘」の濃度が高まる。そういう意味で、分かりやす過ぎる話は、「嘘」の濃度が高いと思った方がいい。メディアが伝えない本当のことをわかりやすく解説します、みたいなネット発信者はいま多々いるが、そういうものも、話半分として捉えるリテラシーが必要だ。そもそも立板に水、というような弁舌は、詐欺師や悪徳セールスマンの基本スキルだし。
子どもがリテラシーを確立していく上で重要なのは、身近な信頼できる大人が、様々な問題、社会の事象をどう考えているか?ということだと思う。だから子どもの「あれってどう思う?」という問いには、できる限り真摯に答えるようにしている。そして、子どもにそれを聞かれるような信頼を得られる親でありたいと思っている。そして結局そのためには、日々、学び続けることが大切だ。
まあそれにしても、USスチールの話は結構難しい。鉄が人類にとって超重要、というところから話を始めると長くなり過ぎる。こういう時は参考図書を推薦するのがある意味の逃げだけど、ふと見ると、この本があった。

出張に行く時に羽田で買った気がするが、残念ながらさほど面白くなかった。(笑)
それよりもこっちか?これは現代人必読?の名著。まだ長女には読ませてなかったかも。ジャレド・ダイアモンド氏が元は鳥の研究者だった、ということで個人的に思い入れが強いということもある。

少しトリッキーだが、このシリーズも面白く製鉄所のリポートも結構渾身の一章だ。



広島時代、自動車業界を本腰で取材しようとした時に、唯一にして最大の参考書となった本。これを精読して初めてサプライヤーとか、製造現場の人と、ある程度の会話が可能になった。福野礼一郎氏の本はどれも面白いのだけど、中でもこれは渾身の名著。カーグラフィックに連載されていたのだが、今や紙媒体でこのような硬派で骨太な記事が生まれるだろうか?
あ、この本は工学系の長女には薦めてもいいかも。

ちなみに本日は、娘送ったあと、仕事休んで母の通院付き添いの日。いつも通り疲れて帰る。気持ちリフレッシュのため、日没前にランニング。大寒なのに寒さが緩んだのか、なぜかコウモリが飛んでいた。

神奈川県葉山町/58歳