冬休み まず木を切る
「木を切れ」というのが、妻からの指令。 彼女が数年前に買ってきて植えたユーカリの一種。当初は全然、存在感がなかったが、最...
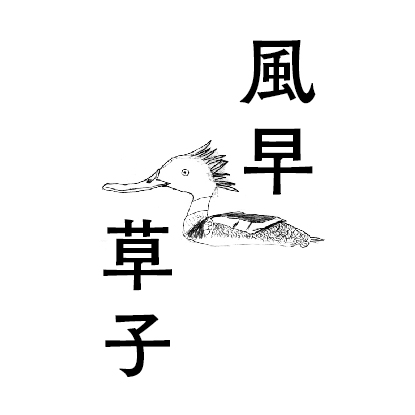
風早草子
カザハヤソウシ
2024年12月18日

庭に「ロケットストーブ」というものがある。3年前に私が作った。ちゃんとした薪でなくても強い火力が得られるコンロみたいなもの。
作り方はネット上に色々紹介されている。それほど難しくなく、材料費も程々で作れる。メインパーツのペール缶は、ガソリンスタンドで頼めばただでもらえることもある。うちのペール缶も一個はENEOSで給油した時にもらった。ただ3年経ち、ENEOSでない方の缶がすっかり錆びてしまった。ホームセンターで買った缶より、ENEOSの方が塗装してあって耐久性が高いようだ。次に作る時は、二つもらってきた方が良さそう。

下の缶は一部、錆びて腐食して穴が開いている。ロケットストーブの内部は、断熱のためにパーライトという多孔質の土壌改良剤が詰めてある。穴からパーライトがこぼれてきている。ただ熱が一番かかる部分周辺だけで、そこ以外はまだ大丈夫そう、ということで修理することに。



高温になるので、熱に弱いものはダメ。アルミテープなども耐えられない。で、使うのが、粘土。雨水が溜まりがちだった庭には雨水浸透用の縦穴を掘ってあるが、底の部分は思いっきり粘土質。ここから掘り出した粘土をペタペタ貼り付けて穴を塞ぐ。粘土は高熱になっても燃えたり溶けたりする心配はない。むしろ焼物になるはず。
修理したので運転しようと、枯れ枝を拾いに山へ。細い枯れ枝とか、剪定されて捨てられるような枝でいい。今の時代、木の枝はゴミ扱いなので、山に限らず拾おうと思えば、そこら中に転がっている。よく乾いていることが一番重要だが、この季節はカラカラなのであまり心配はない。

ロケットストーブは、断熱した煙突内で燃える枝から出たガスが二次燃焼する構造。そのため乾いた枝を燃やす限り、煙や臭いがほぼ出ない。町の広報誌を見ると、最近は薪ストーブの煙や臭いの苦情が増えているらしい。ロケットストーブもよく乾いてない木を投入すると、盛大に煙や臭いが出るので、そこは気をつけているが、これまで庭で使って近所から何か言われたことはないので、まあ大丈夫だと思っている。
そこで冬場は朝、コーヒー用のお湯を結構これで沸かしている。まだ真っ暗な朝5時にそんなことをしているのは、変人の所業だが、大災害に備えた日々の訓練でもあると思っている。あと多少、化石燃料使用を減らしてCO2削減にもなってるはず。

着火はそれなりにコツがある。いきなり枯れ枝に火はつかないので、新聞紙を使った方がいい。油分が多い杉の枯葉も使うのがいい。新聞紙半分と杉の葉一掴み。着火しやすい細い枝を最初は多めに入れる。新聞紙に着火してストーブに押し込む。そして十分燃えた頃合いで、上に上がる炎を煙突内部に向かうように息を吹き込む。炎が煙突に向かうと、投入口から煙突に向かう強い空気の流れができて「ゴオーーーー」という音が鳴り始める。新聞紙と杉の葉が短く強い炎を上げる間に、枝が燃焼を始めればok。マッチ一本で燃焼開始に成功すると気持ちがいい。
新聞紙や杉の枯葉は、燃やす時に多少の煙と臭いが出るので、これを最小に抑えて着火したい。
いったん枝が燃え始めれば、火が消えることはないので、投入口に細い枝、太めの枝、織り交ぜて詰めてしまって大丈夫。10分程度でケトルの湯が沸騰する。


難点は、煙や臭いは少ないが、煤は出るのでケトルが真っ黒になること。普段使いのケトルを使用すると妻に苦情を言われるので、キャンプ用を使う。あまりに真っ黒になったら、クリームクレンザーで煤を落とす。

このロケットストーブ、2021年の12月に作った。春から秋は全く使わず庭で雨ざらしだが、3年経ってまだ使えることが確認できた。一応、災害時の備えとして機能は保っている。ライフラインが止まるような災害はもちろん起きて欲しくないが、モノと心の備えは日々、考えておく必要があると思っている。

ちなみに2度湯を沸かして熱したら、粘土で塞いだ部分はこんな感じ。穴が塞がっていれば十分。

神奈川県葉山町/58歳