追いキュウリ
次男は朝6時半に模試に出かけ、双子は今日は友達と遊びに行く。妻は昨日の盆踊りの疲労でややぐったり。引き続きナンバー特別編...
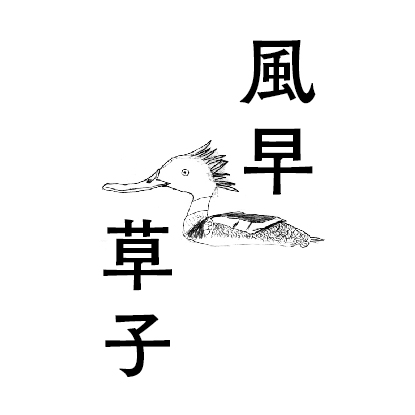
風早草子
カザハヤソウシ
2024年11月27日

妻がこの本を買って読んでいて、面白いと勧められた。結構面白い。そして大切な話だ。新しい言葉が定着して、その概念が広く認知される様になるのはいいことだと思う。セクハラとかパワハラとかもそうだし。ただ、心理的安全性については、言葉がメジャーになる前から自分では意識してきた自負もある。
十数年前、40代前半で管理職として広島に行った時、現地採用の20代のディレクター・キャスター7〜8人を部下に持つことになった。一人が男子であとはみな女子。3月まで大学生でした、みたいな素人同然もいる。でも担当企画は膨大。当然、職場は自転車操業で徹夜とか休日出勤が横行する状況。前任者はそのメンバーに対して鬼デスク気取りでパワハラ的指導をしていたので、辛くて途中でやめるケースもあり、グループは不安定だった。まあ端的に言えばブラック職場だった。
さてどうするか?
問題は山積だったが、まずとにかく若いチームのメンバーに安心して仕事をしてもらうことが必要だった。そこで決めたのが、「怒らない」を徹底すること。これは怒鳴らない、とかネチネチ説教しない、という単純な話ではない。
どんなに???な提案や構成を部下が持ってきても、ため息をついたり、舌打ちをしたり、不機嫌な表情を見せたり、嘲笑したり、ということを一切しないことだ。職場にいる時、「この人はいま不機嫌なのかな?」と部下に相談を躊躇させる様なそぶりは絶対に見せない様に自分を律する。どんなに疲れていても、忙しくても、「あの・・・」と部下に声をかけられたら「いいよ!」と答える。それを徹底した。
元来、私はあまり優しい人間ではない。子どもの頃から勉強はできたが、人には冷たいタイプ。プライドが高くて冷めていて、失敗して困っている人がいても「自己責任だろ」みたいな感じ。冷笑的で、簡単に言うと、結構嫌なやつだった。爆
でも当時、結婚して子どもが生まれて、親として子育てする立場になって、今までの様な冷たい人間ではいけないと思っていた部分もあったと思う。根が冷たくて嫌な奴ではあるが、優しい面倒見のいい人間を演じようと頑張った。
性格が悪い人間が周りを欺こうとしているのだから、やり方は周到である必要がある。愛されキャラの天然上司が天真爛漫に暴言を吐いても許される、みたいなのとは真逆。周りからどう見られているかは徹底して考えた。ため息つかない、舌打ちしない、乱暴にキーボード打ったりしない、とか。もちろん企画の相談、私生活、人間関係の悩みも全て正面から受け止める。優しさ云々ではなく、そう決めたからだ。家で双子も生まれて私生活も非常に大変な時期だったが頑張った。
でもその効果は効果は大きかった。どんなことでも怒られない、助けてもらえる、となると安心して相談に来てくれるので、どんどん情報が集まってくる。結果、先手先手で対処も可能になる。20代のかわいい女子たちなので、そもそも日々、色々起きる。他部署の単身赴任の管理職からショートメールがやたら来て食事にしつこく誘われて困っている、とか。面倒な案件だが、こういうのは即座に対応しないと、信用されなくなってしまう。私より先輩の方であったが、トイレに立ったのをつけて廊下で待ち伏せ、階段室に連れ込んで問いただした。土下座する勢いで謝罪されたので、上まで上げなかったが、「次は無い」と警告してケリをつけた。
面白いもので、そういうことをしていると、本来、優しくもないし、不親切な人間の私のところに他部署の若い女子たちからも相談が寄せられる様になる。直接の上司が信用されていないからだ。私の役割ではないのだが、実直さで部下の信頼を得てグループを回すのが目的なので、放置はできない。そういうのも全部対応した。まあ他部署の情報が分かるのは色々有利なのでメリットもあったが。
ただ、嘘も3年、4年とつき続ければ、不思議なもので、だんだん真実に変わっていく。最初は意識して優しい人のふりをしていたのだが、途中から演じてる感覚はなくなり、自分は昔から親切で優しい人間だったのでは?と錯覚すら感じた。違うんだけど。でも多分少しは優しい人間へと成長できたのだと思う。
ちなみに4年間で、部下は一人もやめなかったし、メンタルにもならなかった。そして若手女子ばかりのチームは社内だけでなく、他社からも一目置かれる最強チームに育っていった。彼女らは卒業後も各方面で活躍している。私の密かな誇りだ。
ちなみに本の中には例の「1on1」についてもやり方などが書いてある。当時、1on1という言葉は知られていなかったが、これも当たり前にやっていた。ディレクターという仕事は責任も負担も重い。しかし現場に出してしまえば、もう任せるしかない。何を任せられるのか?どこまで任せられるのか?どこまでなら頑張れるのか?どうなったら助けに入るべきなのか?そういう見極めは、一人一人と普段から対話して、その人間を知っておかなければできない。どこの町でどんな両親に育てられたのか?どんなことを面白がり、どんなことに腹を立てる人間なのか?根掘り葉掘り聞いてばかりいると嫌がられるものなので、自分の思っていることや、最近感じたことなども話しながら、相手の考えを引き出していく気遣いが必要だ。そして自分がどんな人間か?というのを部下に知ってもらうことも大切。価値観をさらけ出さないと信用は得られない。その信用を得るためには、日常の行動で示す必要がある。家族を大切にするとか、約束は必ずか守るとか、時間に遅れないとか。
そういう意味では、1on1、というのがあたかもテクニックの様に本に書かれていると少し違和感も感じる。個人的には当たり前のことであり、逆に1on1ができていない部下には、怖くて仕事など任せられない気がする。
以上、妻の本を見て57歳が思い出したことと感想でした。
1on1は、もちろん今の仕事でもやっている。これは妻や子ども、家族とやることも大切だと思う。そういう意識は特別しなくても。

神奈川県葉山町/58歳