「この世につまらん仕事なし。」イチハラヒロコ恋みくじ/第十九番
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...
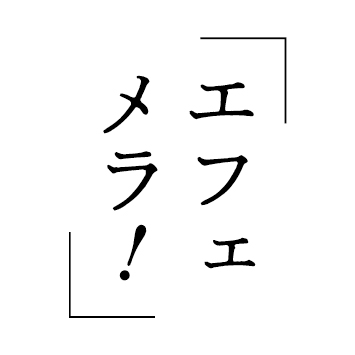
エフェメラ!
エフェメラ!
2025年9月3日
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶともなしに記録しようと思う。言葉は儚いものであるからこそ、今このときを確実に残してくれるから。
「『ああ, これが戦争が終わったということなのだなあ』の実感は, 当時の丸山眞男氏の言葉であった.」
『みすず書房の50年』「1946」の項
まとまった連絡仕事が続いている。楽だけどとにかく面倒で、気分を変えようと出かけることにした火曜日。久しぶりで三鷹の『水中書店』を覗くのはどうか。そしたら昼は『みたか』で中華そばにしようか。いくつか電話しなきゃいけないので、テラス席があって『みたか』から近い『ドトール』で作業すればいいなと思ったところで、三鷹行きを決める。
中華そば食べて、テラス席で作業。途中「迎さん」と声をかけられ、視線を上げると詩人で翻訳家のKさんがいる。一度飲みの場でご一緒してから、アルバイト先の書店に来てくれたり、詩の朗読会に呼んでくれたりと付き合いがある。散歩の途中だったそうで、軽く話して別れる。こういうすれ違いが起こるのはいい。テラス席、積極的に利用していこうかな。
仕事がひと段落したところで、『水中書店』へ。『G・スタイナー自伝』『みすず書房の50年』買う。店主のKさんと久しぶりに話す。国立の『ブックオフ』の閉店、『三日月書店』の移転などについて。夕方ごろ店を出て、もう少し仕事したいけれど、帰宅ラッシュに巻き込まれると面倒なので、西国分寺まで移動する。
駅前の『プロント』に入り、さっそく『みすず書房の50年』をひらく。2冊本で、1冊は「刊行書総目録1946-1995」(自分の生まれ年に刊行された本を眺めるだけで面白い)、もう1冊は創業した1945年から1年ずつの歩みを振り返る冊子「みすず書房の50年」。例えば、1946年の項にはこんなことが書いてある。
「片山敏彦装幀の白カバー・デザイン, その鼠・黒・朱の三色のとりあわせは, 店頭に立つ読者に新鮮な本のインパクトを与え, 『ああ, これが戦争が終わったということなのだあ』の実感は, 当時の丸山眞男氏の言葉であった.」
強く、時代の変化を感じさせる証言だ。「白カバー・デザイン, その鼠・黒・朱の三色のとりあわせ」といった、みすず書房らしいシンプルな本の佇まいは今でも当時と変わらない。ただ、今の読者にとって(少なくとも僕にとって)、その佇まいは、クラシックで格式を感じさせるものだから。(034)
エフェメラ/「一日だけの、短命な」を意味するギリシャ語「ephemera」。転じて、チラシやポスターなど一時的な情報伝達のために作成される紙ものなどを指す。短命だからこそ、時代を映すとされ、収集の対象になっている。