「平和や平等を叫ぶ人間が完璧でなくてはいけない、なんてそれこそ平和や平等に反する、と私は思う。」柚木麻子
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...
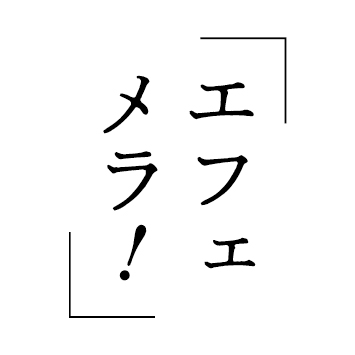
エフェメラ!
エフェメラ!
2025年8月15日
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶともなしに記録しようと思う。言葉は儚いものであるからこそ、今このときを確実に残してくれるから。
「わからないというのはどうわからないのか、それを述べて意見のかわりにしたいと思う。」
伊丹万作「戦争責任者の問題」
アルバイトをしている書店で、一昨日、「戦後80年」に関連するフェアがスタートした(事前に「太平洋戦争敗戦関連の書籍を集め」る、と連絡があったけれど「80年」という言葉は必要だと思っている)。先日も書いたとおり、いま棚には「戦後80年・昭和100年」の単語が溢れていて、さらに輪をかけて「戦後80年・昭和100年」本(と言ってしまう)のセットが出版社各社から送られてきている。
これとは別に店員ひとりひとりも選書しましょうということで、とりあえず雑誌『世界』の8月号を挙げていた。そして、なにをどう選べばいいのか、今だに考えている。悩んでしまうのは、たぶん、普段は「なにがどう並んだら楽しそうか」を軸にフェアを考えているからだと思う。その点、当然、戦争は楽しくないので。
考えてるだけでは埒が明かなそうなので、ひとまず体を動かそうと、一昨日、フェア台に並んだ本に触発されて、いくつか本を並べてみた。坪内祐三『靖国』、大岡昇平『野火』など。そして反射的に、こんなことを思う。
……環太平洋のスケールでこの80年の歴史を辿る本を並べるのはどう? あ、そういえば最近なにかで「日本が戦争していないからと言って、世界で起こる/起こってきた戦争と無関係ではいられないのだから、『戦後80年』とは不思議な表現だ」みたいな内容の文章を読んだけど、この80年間の戦争と日本の関係がわかる本を並べることもできるかもしれないなあ……
遠回りしたけれど、引用は1946年に書かれた伊丹万作の一文のさわり。アルバイト先の書店のLINEで、さきほど共有されたテキストだ。まだみんなも選書に悩み続けているみたい。(015)
エフェメラ/「一日だけの、短命な」を意味するギリシャ語「ephemera」。転じて、チラシやポスターなど一時的な情報伝達のために作成される紙ものなどを指す。短命だからこそ、時代を映すとされ、収集の対象になっている。
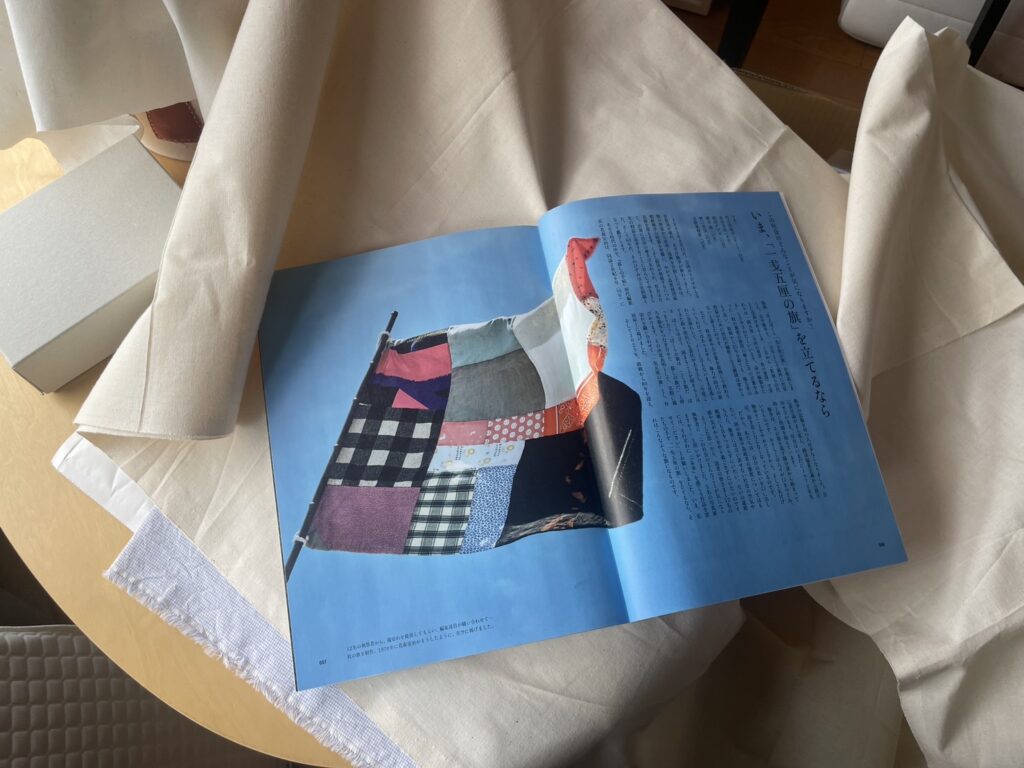
アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...

アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...

アルキメデスは浴槽から溢れる水を見て「ユリイカ!」と叫んだ。私たちは日々見聞きする言葉に触れては「エフェメラ!」と叫ぶと...