連休明け
快晴の連休明け。シジュウカラの親鳥が目まぐるしく、餌を運んでいる。ヒナたちは順調に大きくなっている。餌は青虫が多い。この...
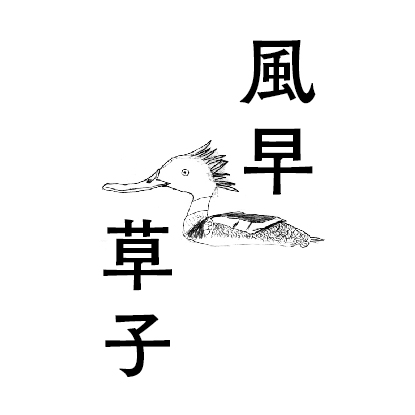
風早草子
カザハヤソウシ
2025年10月29日

今度は岩手大学にクマが出たという。盛岡は2年前に出張で行った。その時もかなり市内をランニングして岩手大学も見た。完全に街の中だ。盛岡第一高校と隣接していた。比較的近くに高松の池、という林と池があるが、その間には普通に市街地がある。北上川は大学から見ると盛岡駅とか線路の向こう側で河川敷は近くない。
先日クマが出たという秋田市の千秋公園も出張の時に走ったので、イメージはある程度把握できている。盛岡にしても秋田市にしても、尋常ではない状況だと思う。
根本的にはクマの数が増えている、というシンプルな問題だと私は思っている。これだけクマがニュースになると、ニュースだけでなく、ワイドショーや雑誌、ネットメディアなどで、様々な「専門家」の見解が流布される。適当な話も多いので話半分に聞かないといけない。昔から野鳥や野生動物、自然に関するテレビや新聞の報道は全てとは言わないが、嘘やデタラメだらけなのである。私は自身が野鳥に興味を持つようになり、自分で見聞きするのに加えて、幅広く野鳥に関する知識を吸収する中で、すでに小学生の頃にそれに気付いていた。父が新聞記者だったため、日常的に新聞をくまなく読んで記事をハサミで切り抜き、膨大なスクラップを作っていた。その時に、野鳥に関する記事を見つけると切り抜いて私にくれていた。だから私も、野鳥とか自然保護に関する膨大な新聞記事を読み、スクラップとして保有していた。それを見ると、小学生の私でもわかる間違いがいくつもあるし、見当違いのコメントをしている「専門家」が山ほどいる。小学生ながら、私は「あー、こういう記事は正しい専門家も見極められないレベルの記者が書くものなんだなー」という現実を悟ってしまっていた。そういう目で見始めると、動物番組の編集なんてヒドイものだ。草原で草を食べるウサギ、それを見つめるワシの表情のアップ、警戒して頭を上げるウサギ、枝から飛び立つワシ、逃げるウサギに襲いかかるワシ・・・全部違う場所だろ!みたいな感じ。そもそもワシがウサギを襲う瞬間を撮れたとして、その前後のそれぞれの表情を押さえるカメラなんて現場にあるはずがない。まあでもワシもウサギもテレビ局に抗議の電話はかけてこないので、動物番組の編集なんて、少なくとも昔はやり放題、嘘つき放題だったのである。
若干、話は逸れたが、まあたくさんクマが出てくるのは、クマが増えているから、というシンプルな話で、根本的な対策はまず駆除して個体数を減らすしかないと私は思う。里に野生動物が出てきて人間に被害を及ぼす、というニュースが出ると、必ず「人間が山の環境を悪化させたため、山に餌が乏しくて動物が里に出てくる」という人間悪玉説を言いたがる「専門家」が出て来がちだが、それも見当違いだと私は思っている。1950年代以降、奥山の広葉樹林を皆伐しまくって、杉やヒノキに植え替える拡大造林の時代ならそうかもしれないが、そういう流れはもう30年くらい前に終わっている。私が近畿地方の里山で環境アセスメントの調査をしていた1980年代の時点ですでに拡大造林で植えられた杉、ヒノキの林は、安い外材の流入で採算が合わなくなり、枝打ちなどの手入れをされないまま荒れ果てていた。そしてそういう里山に入っても、誰一人、人間に遭遇することはなく、山は藪に覆われていて、調査のために歩くには、「藪漕ぎ」が必要だった。昭和30年代、農村で風呂や炊事の煮炊きに薪が使われていた時代、里山というのは、年中枝や草が刈り取られてスカスカのハゲ山に近いようなところばかりだったと聞く。しかし、1980年代、すでに行手を阻む薮が生い茂る緑の魔境だった。そんな場所を私が調査していたのは、ゴルフ場開発のための環境アセスメントだったのだが、結局バブル崩壊でほとんどの場所は開発されなかったため、藪化した里山は全国にたくさん残り、イノシシやクマが人里の近くに出てくる橋頭堡となっていったのだと思う。
よくニュースで今年はブナの実が凶作で山に餌がない、みたいな話も出るが、山の木の実の成りが年によって大きく違うのは普通の自然現象だ。毎年同じ量が実ったら、それに合わせて増加する動物に全部食べられてしまうから、豊凶の差を大きくして、豊作の年に食べ尽くせないくらい実を落として子孫をのこす樹木の生存戦略だろう。それに適応して、別の餌を探しに行くのはクマなどにとって普通の行動であり、可哀想、というようなことではない。でも、山の餌が今年は凶作で、という報道のトーンにどうもそういうニュアンスが付きがちなのは気になる。
まあしかし、出てきたクマがこれほど人を襲う理由はなんだろう?と気になる。数年前、秩父で山の険しい稜線を歩いていた登山者が、突然熊に襲いかかってこられる衝撃的な映像が、登山者がつけていたゴープロで記録されてYouTubeに公開されたことがあった。登山家が咄嗟に反撃してかろうじて無事だったようだが、襲われても滑落しても死亡しかねない恐ろしい映像だった。ただ歩いていて、いきなりこれではたまらないという感じだった。このクマは子連れのメスグマだったようだ。昔から子連れの母グマは危険だと言われているが、なぜ母グマがそれほどナーバスか、というのは、オスグマを警戒しているからだろう。メスと交尾をしたいオスグマは、メスの発情を促すために子連れのメスを見つけると、子グマを殺そうとすることが知られていて、そういう実例も記録されている。山の中で明確に殺意を持って襲ってくる「敵」がいるのだから、ナーバスになるのは無理もないけど、子グマを殺そうなんて思わない人間にまで襲いかかってこられるのは迷惑な話だ。ただ、メスグマの場合、クマの生息数が増えて、山の中の危険なオスグマの密度が上がって来たら、オスグマが少ない人里へ向かうモチベーションは十分ありそうな気がする。ただ襲った人間を食べたり、飼い犬を襲って連れ去ったりするクマの行動はまた少し違うような気がする。ただ、これだけ人間が襲われて、飼い犬まで連れ去れらる状況だと、そのうち人間の子供とかに犠牲が出るのではないか?という危惧の声も見た。そういうことまで起きないように対策は急ぐ必要があると思う。

神奈川県葉山町/58歳