夏休みの終わりに
長く取った私の夏休みも今日で最終日。朝5時に家の窓を開けたら、涼しい風が入ってきた。昔は夏でも朝のラジオ体操の時間頃まで...
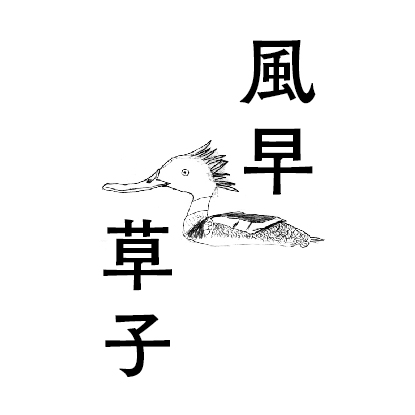
風早草子
カザハヤソウシ
2025年11月26日
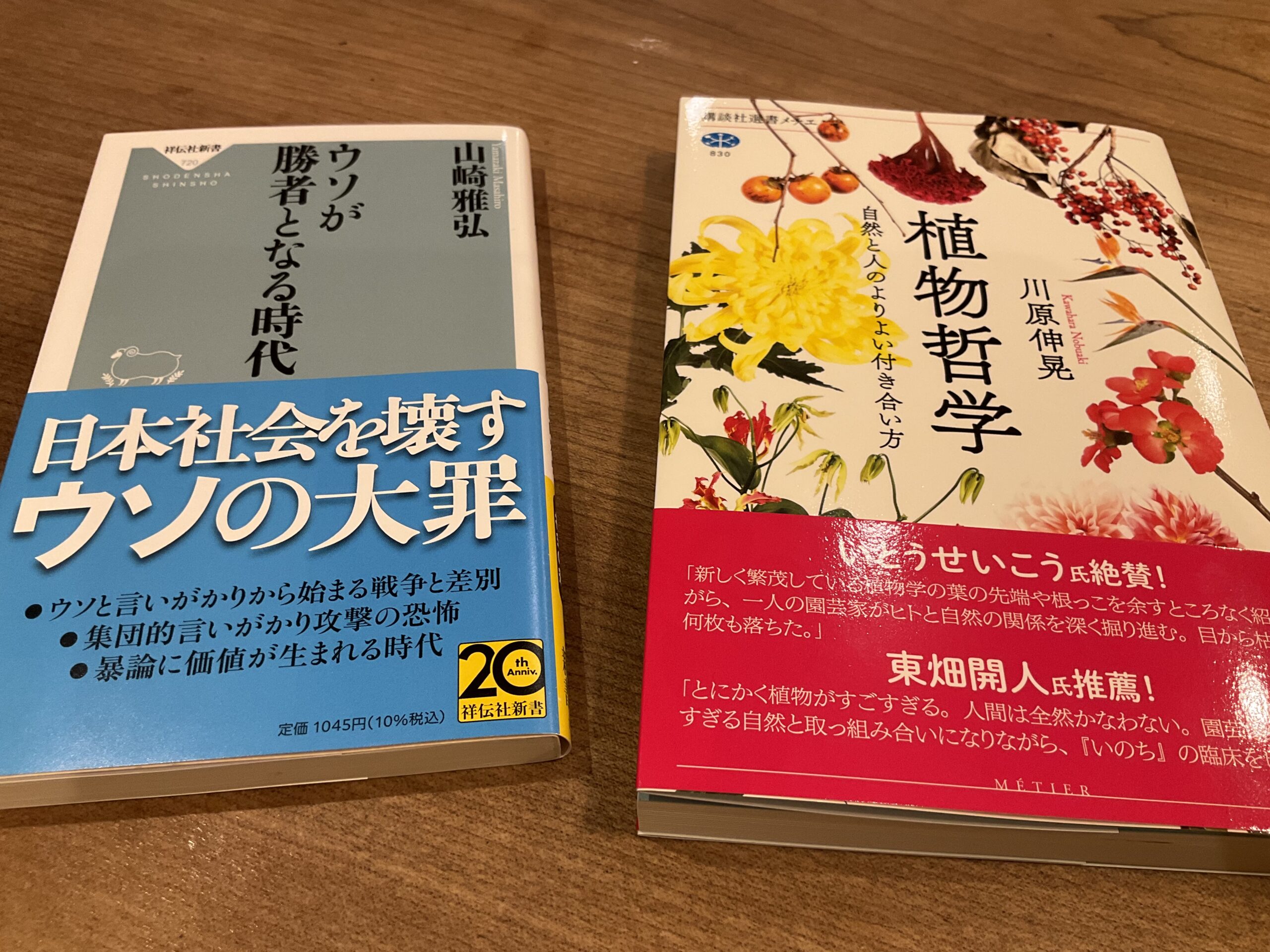
妻が武田砂鉄のラジオで聴いて「こういうの好きなんじゃない?」と薦めてきた本は「植物哲学」の方。本屋でめくって、そこまで私の趣味ではない気もしたけど、薦められた本を読んでみることも時には大切かも?と購入。左は、これも妻が聞いていた武田砂鉄のラジオで聞こえたタイトル。こっちは割と、仕事に直接的に関係するので、ざっと見ておくべきか?
植物哲学の方、園芸左翼と園芸右翼、二重スパイ、という独特の表現で、好きな植物を商売の材料として消費する園芸家の葛藤みたいなものに向き合っている。右翼、左翼の比喩が最適かは置いておき、植物至上主義をサヨク、人間優先主義をウヨクとしている。例え話にジャンプの漫画やジブリ映画が多い。私は分かっているので理解できるけど、幽遊白書を持ち出して理解できる世代、男女の幅はどのくらいだろう?
こういうウヨク、サヨクみたいな感じは、私が身を置いてきた自然保護関係の世界にもありがち。一木一草を切るのも1匹殺すのも悪、みたいな極左?みたいな観念的なことを言う人もいる。それは自然保護ではなくて、動物愛護とか宗教ではないかと思うけど。私は取り返しのつかない乱開発などが行われず、調和ある自然がトータルで保たれる状況を目指す穏健派。増えすぎた熊や鹿は撃てばいいし、ルールを守って狩猟された鴨肉を食べることに抵抗はない。
ただ右翼でも左翼でもいいのだけど、最も罪深いのは、ちゃんとした事実を知らずに意見を言うことだと思う。この秋、熊をめぐって様々な意見がメディアやネットで飛び交っているが、ピントハズレでバイアスのかかったものが非常に多いと思う。そもそもの現状認識が間違っているものも多い。ありがちな幻想の一つが「里山」という概念。1995年に出た今森光彦さんの里山物語という写真集が大変素晴らしく、その言葉が普及した。山に囲まれた水田、いわゆる谷津田というやつだが、その周囲にはクヌギやコナラの林が広がり、田んぼに水を供給する水源となり、またその緑肥は肥料となり、枝は椎茸のホダ木になる、そしてその林にカブトムシやクワガタが育つ。みたいな持続可能な調和の取れた人里のシステム、みたいなイメージだ。でも昨今の熊論議、こういうイメージを元に、人間が山を壊した、とかメガソーラーが、とか、いった主張も目立つ。だけど、ちょっと調べれば分かる話なのだけど、調和の取れた里山というシステムが全国の村落で機能していた、というのは幻想だ。今森さんが撮影したフィールドであの時代にそういうシステムが回っていたところはあったのだろう。でも一般的には人里近くの山は過剰伐採で慢性的にハゲ山に近かったのがほんの昭和30年頃までの現実だ。そりゃ、煮炊きや風呂の燃料も、農地に入れる落ち葉や緑肥も全部山から取って村人が生活していたらそうなる。持続可能とか言ってる余裕はなくアップアップな生活だったはずだ。菜種とか綿とか商品作物には蝦夷地から入るニシンとか高価な金肥も使われていたようだが、日々の食糧は人糞とか草木の緑肥しかなかったはず。実際、江戸中期以降は全国の人口は頭打ちで東日本は減少すらしていた。
また山林の荒廃という意味では、戦国時代以降盛んだった製鉄の影響も大きい。当時の製鉄は鉋流しという手法で砂鉄を集めることから始まるが、簡単にいうと、花崗岩の山を切り崩して丸ごと水流に流すようなものだ。途中の沈殿池で重い砂鉄を濃縮して材料を得る。軽い土砂は川の水流に乗せて海まで、という乱暴なものだ。広島では城の堀が埋まってしまい、大田川が浅くなってしまうので、江戸時代に大田川上流での鉋流しを禁じている。しかし、それまでに流れた土砂の量は膨大で、実際、現在の広島市の主要地域のデルタはほとんどこの時代以降にできたものだ。また製鉄は鉄を溶かすのに大量の木炭が必要なので、鉋流しとは別に奥山で大量の木も伐採された。当然、木が伐採されれば、流出する土砂も多くなる。実際問題、現在、山陽も山陰も中国地方に広がる平野の多くは、江戸時代以降の製鉄で流出した土砂で形成されている部分がかなりの割合を占めていると考えられているのだ。その結果、海岸部には分厚い砂浜が形成されたのだが、江戸時代、この砂は風が吹くと飛砂となり集落や農地をあっという間に埋めてしまうなど大きな被害を出すことになる。その対策として各地で植えられのが海岸の黒松林の防風林となる。つまり白砂青松、というのは日本の原風景みたいに言われることもよくあるが、歴史はそれほど古いものではない上に、そもそも原因は人間の乱開発にある。
「里山」というもの。私は学生時代、環境アセスメントの調査で、京都、兵庫、三重、奈良など各地でずいぶん山に入り歩いた。現役の里山ではなく、成れの果ての里山だ。藪漕ぎしないとルートが作れないなかなかタフな仕事だった。バブルの時代、こうした山は経済的な価値を失った一方、企業や銀行には金が溢れて、貸出先もなく行き場を失っていた。そうした金の向かい先が、会員権販売という方法で手っ取り早く資金が回収できるゴルフ場開発だったわけだ。当時聞いた噂では、三重県では県の面積の30%くらいの土地にゴルフ場計画があるということだった。真偽は分からないが、それもありなん、というほど、環境アセスメントの仕事は多かった。大学で生態学の研究をしていた人がアセス会社をあちこちで作り、鳥がわかる人なら誰でもいい、という感じで私のところにも破格の高報酬で仕事が来ていたわけである。ただこうした乱開発の先棒を担ぐ形で金を得つつ、私は自然保護団体である日本野鳥の会京都支部の幹事で、しかも立場は「保護部」。さすがに現状の乱開発には反対の声を上げなければならないと考えていた。そのために必要なのは、乱開発されされている成れの果ての里山に、いったいどんな鳥などが生息しているのか、という情報なのだが、なんせ金をもらって各地の里山で調査をしているので、頭の中にはそれはいくらでもある。そして私だけでなく、各地でそういう仕事をしている人間は鳥が好きな関係者なので、その気になれば情報はいくらでも手に入る。なので、当時のアセス調査関係者は、すべからず保護団体の二重スパイみたいなものだった。ただ、こうした成れの果てのありふれた元里山、というものを守る理念とはなんだろう?ということに我々は悩んだ。当時の自然保護運動は、絶滅の恐れがあるトキを守れ、とか貴重なクマタカが生息する森を守れ、といった「貴重主義」しか理論がなかった。天然記念物のイヌワシとかがいればいいのだけど、近畿の里山にそんなものはいない。そもそも我々バードウォッチャーだって、芦生の原生林には鳥を見に行くが、南山城のそこらの里山なんて誰も踏み込んだことがなかったのである。ところが、アセス調査のために藪を漕いで踏み込んでみると、結構な種類の鳥がいる。ヤマドリとかアオバトとか。だからそれなりに一生懸命に調査して、こんなにたくさんの種類の野鳥が生息しています。と書くわけだ。でも天然記念物とか、法律などで保護が求められているような鳥はいない。で、結局アセスメント全体の報告書には、「多種類の野鳥が生息しているが特別貴重な種はいない。開発予定地周辺には同様な山林環境があるため、開発による地域生物層への影響は小さいと考えられる」と作文されて、開発のお墨付きになるわけだ。
そういう自然も本当は人間にとって大事なのでは?という問いは立てたものの、その時代、里山は全く価値を失っていた。実際、藪漕ぎをしなければ入れない山はレクリエーションにも使われていないし、数十年前に植林された杉林は間伐も枝打ちもされず、荒れた暗い林になっていて不気味ですらあった。これならゴルフ場にして金に変えたほうがマシと持ち主が考えるのも不思議ではない。結局、そういう価値観は一朝一夕に変えられないため、我々はこうした里山でも当時、生息が増え始めていた「特殊鳥類」のオオタカを使って保護運動を展開することになった。京大理学部の教授が京都府に開発反対の意見書を出し、情報をマスコミにリークして大々的な記事にして、日本野鳥の会京都支部が現地を調査して、京都府と交渉をする、というような展開。毎週末、京大の学生を多数、私が車に乗せて現地へ連れて行って大規模な調査を展開する。でも実は私の豊富な資金源はアセス会社からもらった調査の報酬だったわけだ。開発そのものを止められたわけではないが、当時、かなりの騒動になったので、ある程度の問題提起はできたとは思っている。別に違法な闇バイトだったわけではないけど、日給4万円とか、報酬的にはそれっぽい金をもらいながら、表では自然保護団体の幹部として、交渉窓口をやっていたので、立派な二重スパイではあったかもしれない。
仕事についてからも、一つの私の主要テーマとして、さまざまなものを発信してきたけど、昨今のクマをめぐる論議を見ていると、まだまだ足りない気がする。というか、みなさん、意見を言うなら、ちゃんとした情報を踏まえて発言してほしい。まあ私だって、全ての日本の歴史とか、全国津々浦々の土地利用に精通しているわけではないけど、多少は学ぶことに時間をかけてきた。その立場でみると、あまりにどうか?みたいな声が多過ぎると思う。今回は完全に高齢者のボヤキだけど、思ったことなので、思い出話と共に日記に記録しておく。
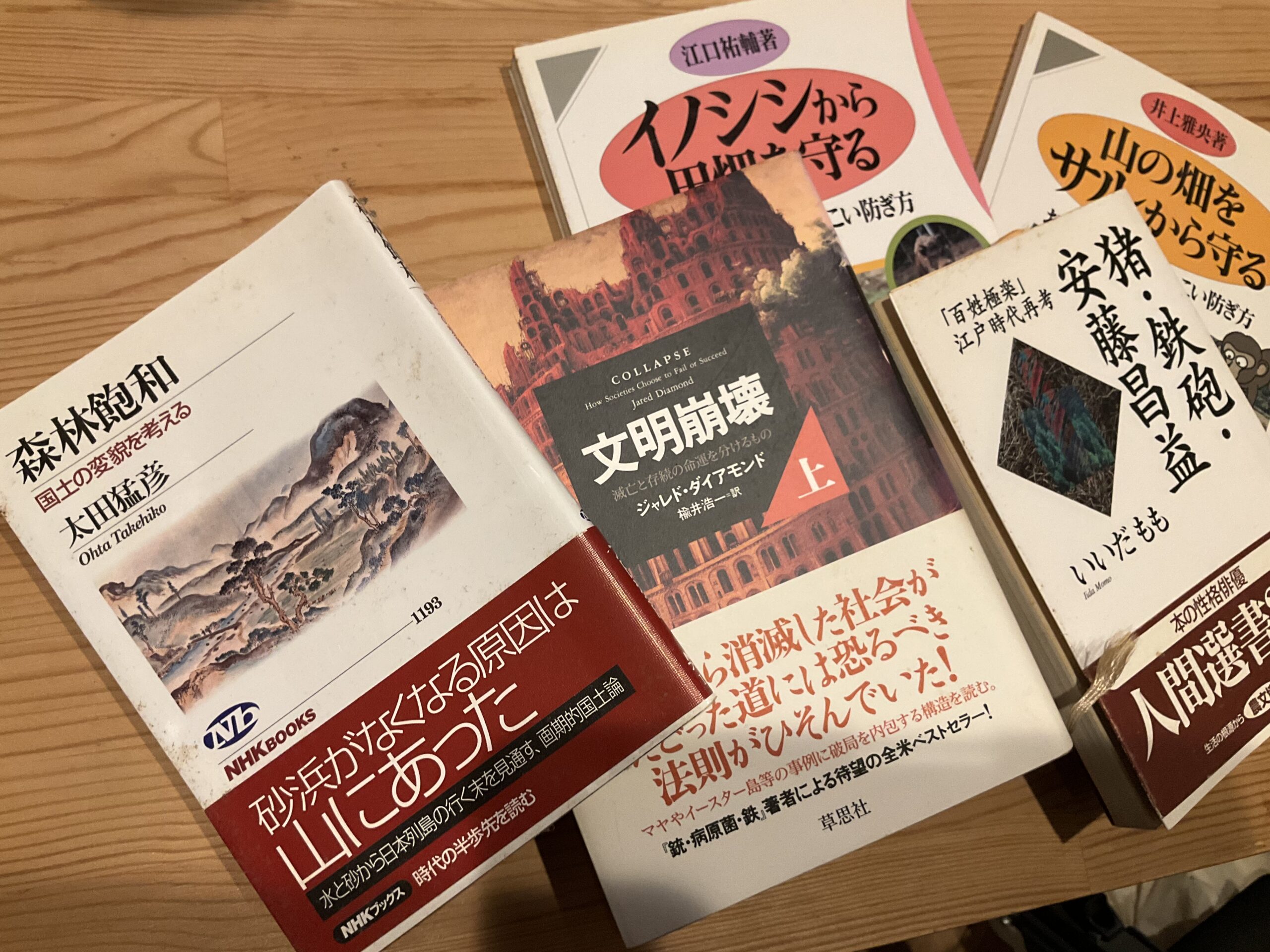
ところで、どうでもいいのだけど、某県の知事が辞職表明だと!
2月までしばらく選挙はないはずだったのに。世の中、油断ならない。(笑)

神奈川県葉山町/58歳