unagi – eel
みんなの鰻の写真に食欲をそそられ、友人と彼女の大学生の息子君、母とソフィの5人でランチ。 わたしの地域では、ひつまぶしで...
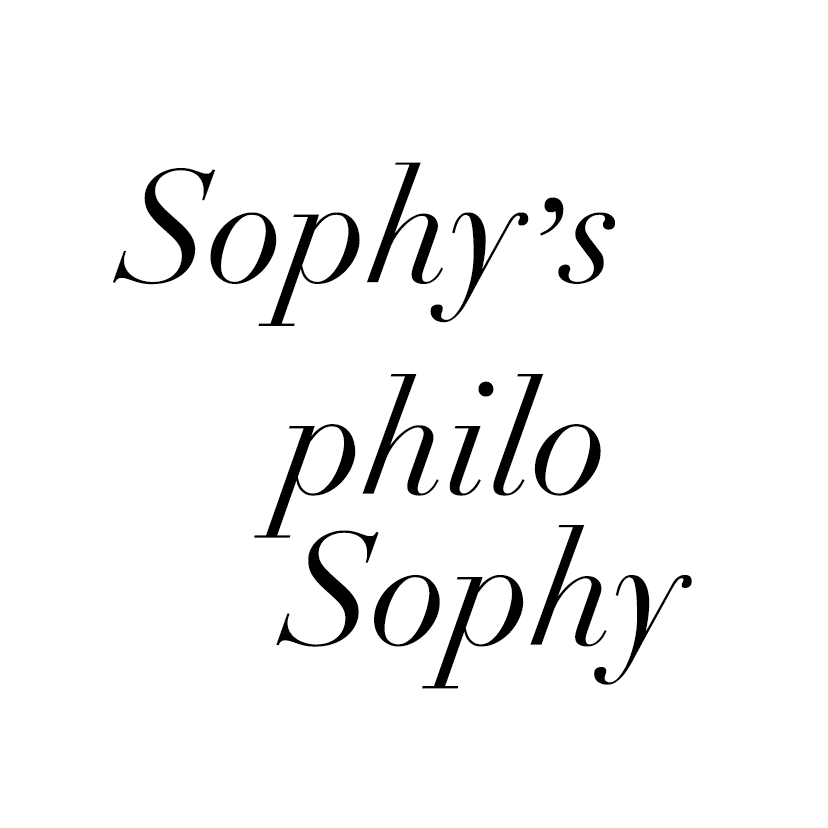
Sophy's philosophy
ソフィーズフィロソフィ
2025年9月27日
王様の耳さん、直線距離9,700キロの空からありがとう。風邪の季節ですよね、良くなりますように。
昨日プールでアクアジムをして、夜にネブライザーをしたらとても回復が早くなったという実感がある。からだを動かせるくらいの風邪だったら、意外と筋肉を温めるのはいいのかもしれないと思った。
昨日参加したオンラインの交流会では、グループ分けを2回して5人ずつくらいで話をした。最初のグループでは、日本の学歴って形だけというか幻想になっていて、本当に必要なことってもっと他にあるのではと思った出来事があった。というのも、国立のめちゃくちゃ入るのが難しい大学の物理専攻で卒業した人が、生活保護を考えているという。彼はたぶん40前くらいだろうか。詳しい経歴はわからないけれど、仕事に就けないのかもしれない。話し方からして特性が強くて今の日本社会だとエンブレースしきれていない属性に入っているのではないかと推察した。
その交流会には、いわゆる大学で講義をする先生や職員さんたちが主に集まる場で、たまにその他の人もちらっと居るくらい。言ったらわたしだって全然関係ない立場なのだけれど、そんな興味主導で参加しているわたしのことも、弾かずに受け入れてくれている。誰でも参加できる、という謳い文句は、飾りではなくて実践されている。
彼の話も、そういう人たちが探り探り質問をしたり、こういう考え方もできるのでは、というような対話をしていた。わたしはそれを、黙って観ていた。正直、ちょっと困惑しながら、自分は今どういう言葉にしたらいいのか迷っていた部分もある。率先してファシリのように話を繋げてくれた人は、どこかの大学の先生だった。慣れもあるのかな。いまのわたしにはできないと思った。
そのあと、別のグループで哲学対話の話になった。最初のグループで一緒だった人とまた同じになったので、さっきはできなかった質問をしてみた。
「こどもと哲学対話をされていると仰っていたが、わたしには自分の娘と哲学対話なるものをするイメージが湧かない」と率直に聞いてみた。するとその人はこう言った。
「身近なテーマで、こう思ったということを、批判ナシで対話するということです。例えばこどもだったら、なぜ子供部屋はいつも整頓されていないのか、とか。哲学対話にはいくつかルールがあって、それを守るだけで、いつもと違う話合いができるので、一度体験してみるとよくわかると思います」
最後のほうに、「何も言わなかったとしても、その場にいるだけで考えを巡らせていることもある」と言われたので、さっきの自分にまさに当てはまると思ったのだった。
哲学対話には以前から興味があったので、少しだけ調べてみた。梶谷真司先生が考えたルールは以下のようなもの。リンクを貼った記事もとても素敵なので、定期的に振り返りたい。
■哲学対話の8つのルール
何を言ってもいい。
人の言うことに対して否定的な態度をとらない。
発言せず、ただ聞いているだけでもいい。
お互いに問いかけるようにする。
知識ではなく、自分の経験にそくして話す。
話がまとまらなくてもいい。
意見が変わってもいい。
分からなくなってもいい。
これなら、子どもと一緒にやってもできそうな気がしてくる。さらには、夫とふたりで、または家族みんなで、という場を持てるようになると、わたしの人生が変わっていきそうな気持が芽生えたのだった。
ふと、レシーヘン宅でソラのことについてみんなで話したとき、実は哲学対話をしていたのではないかという思いが湧いてきた。わたしは批判的態を取ってしまいがちなので、そこをかなり差っ引いたらより哲学対話に近づいていくように思う。またみんなで集まって話したい。
なんだか今の気分にあう写真。スイスのサンモーリッツで撮ったやつ。


イタリア・ベルガモ/46歳